リードステージを定義する際に見落としがちなこと
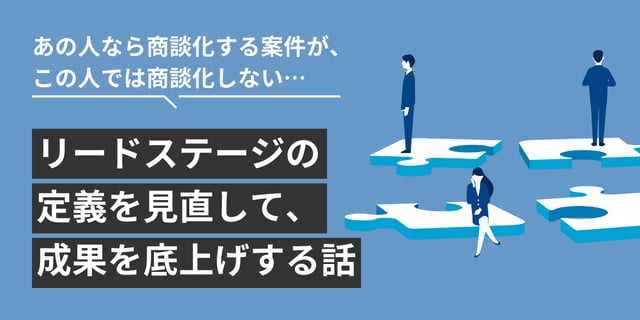
こんにちは、スマートキャンプ株式会社の井塚です。
BizHintとSMARTCAMPは同じグループとして、SaaS業界を中心に累計1000社以上の企業様へマーケティングやインサイドセールスなど幅広いご支援をしております。
私からは、主にインサイドセールの関連情報を発信していきますので、お役に立てば幸いです。
「商談化に苦戦しマーケ・ISの連携が上手く進まない…」
「個人情報を買うだけのリード獲得はROIが悪い…」
部門横断のお悩みでも、ぜひお気軽に当社グループへご相談ください。
ハウスリストを管理する上で、リードステージの定義は必要不可欠です。
リードステージをどのように定義するかで、リストの区切り方も大きく変わってきます。
SFA上でリードステージを入力はしているものの、ステージを使ってリストを区切ったり示唆を得たりはしておらず、実態としては殆ど機能していない、というケースは案外多いです。
今回は、どうしてリードステージが機能不全に終わってしまうのか、リードステージを定義する上で見落としがちなポイントをご紹介します。
ポイント①:可視化したいことが明確になっていない
リードステージを使って可視化したいことが曖昧なため、ステージの数や細かい名称にばかり議論が集中してしまうケースです。
例えばですが、リードステージではリードの状態と優先度を可視化する、のように目的を言語化しておくと、実態に近い定義付けが可能になります。
ポイント②:MECEまたはプロセス網羅になっていない
「このような時にはどのステージを選択するのか?」について、個々人の解釈が揃いません。
迷いが生じないように、MECEであることが望ましいです。
MECEにすることが難しい場合は、
架電→接続→会話成功→商談
といった実際に流れに沿って定義したリードステージで運用できそうか確認することです。
ポイント③:ステージ毎の標準行動が決まっていない
「このステージの時にはこのような行動をする」という標準行動がないと、ステージを入力したのは良いものの、個人で追客頻度が異なってしまいます。
個人で追客頻度が異なると、運用していくにつれて、
- 熱いリードなのに追っていない
- 優先度の低いリードに工数を掛けている
などの会話が多発し、ステージの定義も個々人の解釈に委ねられていきます。
組織の共通言語としてリードステージを機能させるためには、ステージ毎の標準行動まで定義することが望ましいと考えています。
いかがでしたでしょうか?
リードステージの定義には営業企画のスキルセットも求められるため、1日2日でさっと決められるほど簡単ではないかと思います。
より詳細な情報は以下のnote記事にも記載しておりますので、ぜひ参考にしていただけましたら幸いです。
会うべきお客様を明確にしてリードステージを再定義したら未来の商談件数を予測できるようになった話
ご質問やご相談などございましたら、以下のフォームからお気軽にご連絡くださいませ。
またお役に立ちそうな情報があれば、随時発信させていただきます。
この記事を書いた人

井塚 大輔 | X / Linkedin
2022年4月にスマートキャンプ入社。 SaaS代理販売の新規事業にてインサイドセールスチームの立ち上げに従事。KPI233%達成などプレイヤーとして実績を残し、史上最速で半期全社MVPに選出。 その後、セールスエンゲージメントツール「BALES CLOUD」のインサイドセールス部にて部長としてマネジメントに従事し、ナーチャリング経由の商談数を4倍に改善するなどオペレーション作りに実現。セミナーの企画や登壇、新規商談の実施、既存顧客の支援など一気通貫で実施。 現在はSaaS比較サイト「BOXIL SaaS」事業にてインサイドセールスの部長に従事。合わせて全社のテック活用、インサイドセールス代行「BALES」のブランド戦略にも関与し、イベント・研修等の企画や登壇も実施。


